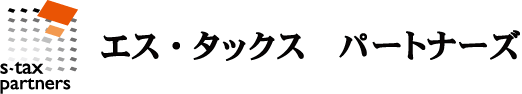- 被相続人名義預金の一部について相続人に生前贈与された事実は認められないと判断、審査請求を棄却(令和6年8月29日裁決)。
- 原資の出捐者や管理及び運営状況を総合勘案して審判所が事実認定を行ったうえで被相続人に帰属する財産と結論付ける。
相続税実務ではいわゆる「名義預金」として被相続人の配偶者や子ども名義の預金が被相続人の相続財産に含まれるか否かが問題となるケースが多く見受けられるが、本事例で問題となったのは、被相続人名義の本件各預金の一部が生前に被相続人の弟である請求人に贈与された事実があったか否かという点であった。この点に関し請求人は、平成14年頃に請求人が被相続人から本件贈与財産(額面1,000万円の小切手と思われる紙面2枚)の贈与を受けたうえでその場で直ちに被相続人に預けたと指摘したうえで、平成23年に被相続人から本件各預金に係る通帳等及び印章を交付され、被相続人に預けていた本件贈与財産の返還を受け、請求人の自宅で保管して管理及び運用していたから、本件各預金は被相続人の相続財産ではなく請求人に帰属する財産である旨を主張していた。
国税不服審判所は、本件各預金は被相続人名義であるところ、預貯金は通常その名義人に帰属するが、その帰属を認定するに当たっては、単に名義人が誰であるかという形式的事実のみにより判断するのではなく、その原資となった金員の出捐者、その管理及び運営状況を総合的に勘案して判断するのが相当であるとした。そのうえで本件における認定事実を踏まえ審判所は、本件各預金は被相続人名義であるうえに被相続人がその原資を出捐し、口座開設日から相続開始日まで被相続人が管理及び運用していたと認められることから、相続開始時点において本件各預金は被相続人に帰属する財産であったと判断している。なお、請求人の主張に対して審判所は、本件贈与財産に係る贈与があったと認めることはできないと指摘して、生前に被相続人から請求人に本件贈与財産の贈与があったとは認められないと判断している。
相続税の税務調査では、被相続人名義や相続人名義の預貯金に係る資金の原資や管理及び運用状況の実態に加えて通帳の入出金履歴などをもとに厳格な判断が行われることを踏まえれば、被相続人から生前に贈与を受けるのであれば、その原資資産を明確にしておくほか、贈与契約書の作成や贈与税申告書の作成・納付に加えて通帳記録の保存などといった客観的な証拠を積み上げて残すことが重要といえそうだ。